音楽家やアーティストが残した名言と人物の物語がすごい
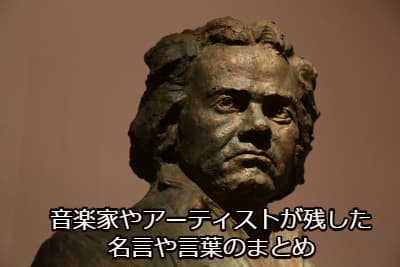
音楽家と呼ばれる人たちは歴史上にたくさんいます。その人がすぐに音楽の世界で有名なることはまれであり、生きているうちは貧しくて生活するのも大変で、亡くなってから有名になるケースもあります。
なので人生で苦労している音楽家の方が多いです。ここではそんな音楽家の残した名言を紹介していきます。
あ行
「完全であること自体が、不完全なのだ」
ウラジミール・ホロヴィッッ(クラシック)
魔法のような独特のタッチとペダリングによって音のバランスを完璧にコントロールし、ピアノで歌うという行為を成し遂げたホロヴィッツ。
弟子には「ミステイクをやってきなさい」と送り出し、自身もコンサートでたびたびミスをすることがあった。
だが、彼の音楽はミスを不問にするほどの素晴らしさだった。
「ほとんど肉体的に堪え難いほど、美しかった」と、ある評論家は記録している。
ミスをする・しないよりも、そのときどきで、音楽を通してなにを語るかを大切にしていたホロヴィッツ。弾き間違いへの追及をかわして述べたこの言葉、ホロヴィッツらしい名言だ。
「現実を模倣することは良きことだ。しかし現実を創り出すことは、なお、なお良きことだ」
ヴェルディ(クラシック)
19世紀、国家統一へ突き進むイタリア民衆の気持ちと共振するオペラを作ったヴェルディ。いまでもイタリアの偉人として慕われている。
この言葉は、1876年、アキッレ・トレッリの《季節の色》を観劇したヴェルディが、ある書簡に記したもの。彼は、同作の軽やかさを評価する一方で、現実の模倣だけになっていて奥行きがないことを指摘し、現実は造り出すことのほうが素晴らしいと述べている。
ヴェルディのオペラといえば、《マクベス》でマクベス夫人役に「くぐもった暗い声」を求めるなど、美しい歌よりも、リァリティのあるドラマに重きをおく。
そのヴェルディのリアリティは、単に現実を棋倣したものではなく、あくまでも造り出されたリアリティだった。
彼は、人びとを真に惹きつけるリアリティを探求していたのだ。
「親のほうが子どもから得ることがよっぽど多いですよ。それと同じで、教えるということはとても勉強になる」
小澤征爾(クラシック)
1959年、ヨーロッパに単身乗り込んで武者修行した小洋征爾は、カラヤン、ミュンシュ、バーンスタインといった世界的な指揮者に認められ、師事した。その才能に特に惚れ込んだバーンスタインは、小澤のことを「永遠の苦い指揮者」と評している。ここでの苦いとは、いつまでも音楽的真実の追求をやめず、勉強することをやめない、という意味である。
1978年、すでに二児の父となっていた小澤征爾があるインタビューで語ったこの言葉は、母校の桐朋学園やボストン・シンフォニーの音楽学校で教えるなかで気づいた実感だが、いつまでも好奇心旺盛に、どこまでも謙虚に学ぼうとする小澤の姿勢がにじみ出ている。バーンスタインが見抜いた小澤像の極致である。
「重大なことというのは、愛し愛されること、幸せになり、充ちたりた気持ちになれることです」
エディット・ピアフ(シャンソン)
自ら「ふたり分の人生を生きた」と回想するほど、ピアフの人生は波乱万丈だ。
16歳で配達夫の少年と恋に勝ち、出産(子供は2歳で死亡)。18歳のとき、有名なキャバレー「ジャニーッ」のステージに立つと、一夜にして成功をつかみとるが、その矢先、オーナー殺人事件の容疑者に仕立てあげられ、辛酸をなめる。
作例家レイモン・アッソの支えもあって、栄光の階段を登り、戦後は、プロボクサーのマルセル・セルダンと愛を育む。だが、マルセルは飛行機事故で死亡。追い打ちをかけるように二度の自動車事故、麻薬に溺れる日々、自己破産。
そこからピアフは不死鳥のごとく復活した。アメリカ、南米ツアーで国際的スターの座を獲得。歌手ジャック・ピルスと結婚。
そして、死の予感ただよう47歳のとき、彼女は二度目の結婚を決断する。相手は20歳も年下の青年……。
笑、非難、侮辱、それがどうした。ただ、ピアフの胸のうちにあった確信がこれだった。
愛と歌にすべてを捧げた女の言葉は、あたたかく重い。
結婚の1年後、ピァフは安らかに逝った。
「ふつう、女性と知り合い、うまくいっているときに、何か創造的なことが起こる」
エリック・クラプトン(ロック)
ヤードバーズ、クリームをへて、あっというまにトップギタリストに登りつめたエリック・クラプトン。いまもギターの神様としてロック界に君臨する。
この言葉のとおり、彼の創作意欲をかきたてるのは、たいていは女性だった。曲作りの相手となるソングライターでさえ、女性を指名する。
かなわぬ恋の苦悩をつづった曲もある。〈いとしのレィラ〉だ。この曲は、親友ジョージ・ハリソンと、その妻パティ・ボイドとの三角関係の果てに、ついえた愛の絶望を書いたもの。
すると、その執念が通じたのか、パティはハリゾンと離婚し、クラプトンのもとに転がりこんできた。だが、まもなく破局。それでもなお、パティのことが頭から離れないクラプトンは、〈オールド・ラヴ〉を書く。
「いままで人生は、山あり谷ありだったけど、それらがみんなパティにつながってしまうんだ」
クラプトンはもらしていた。
「考え方はね、やっぱまあ、無理矢理でも自由にしないと」
奥田民生(ロック)
奥田民生のこの言葉は、ユニコーン解散直前、ドラマー西川の脱退表名をクールに受けとめて語ったもの。
バンド・ブームの波にのって大ブレイクしたユニコーン。面白いものを作っていくには、そんな人気バンドの枠組みを解体することもそぐわなかった民生。
長年バンドを維持するローリング・ストーンズに美学を感じる反面、「無理矢理でも、自由にしないと」と、表現スタイルを柔軟に変貌させることをのぞむ。
その結果が、奥田民生=だらだら、というイメージである。
感じのいいプロデューサーとしてPUFFYの大ヒットを生み、井上陽水とのユニットを試みる。汗臭いロッカーのイメージを脱した彼の音楽活動は、軽さと、ゆるさがつきまとう。それでいて、日本の音楽シーンに確固とした存在感を示している。
レコーディング・ライヴ、演歌歌手・石川さゆりとのコラボ、だらだらイメージをまといながら、民生の闘争はつづく。
か行
「人は指でピアノを弾くのではなくて、心で弾くということです」
グレン・グールド(クラシック)
20世紀半ば、天才ピアニストとして名をはせたグレン・グールドは、キャリアの半ば、32歳でコンサート活動から完全に身をひき、ファンを失望させた。
川間から隔絶し、ひきこもりを先鋭化させるグールド。それは現実からの逃避ではなく、音楽的意味における意識的な行動だった。
グールドにとって音楽は、外の世界のためのものではなく、白分自身の内部でおこる秘かなの。それを外にひっぱりだすコンサートは、グールドにとっては、おぞましいものだった。
グールドは、自分の内部でピアノと同化し、音楽に生命を与える。「心で弾く」とはそういうことだろう。ピアノは、指でたたく外部の固い物体ではなくなる。
あえて孤独におぼれ、マニアックなまでに創造性を極めたグールド。亡くなるまで、音楽渦動の大半はレコード録音にそそがれた。
「人生で素敵なものは、花と女とロマンスだよ」
コンバィ・セグンド(ギター・ヴォーカル)
世界最高齢バンドとして脚光をあびたキューバの「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」。なかでも最年長だったコンパィ・セグンドは、白い帽子をかぶり葉巻を手にし、スーツで決め、そのダンディズムがひときわ輝いていた。
アフリカから連れてこられた奴隷の家系で、音楽だけでは食べていけず、床屋、ペンキ塗り、葉巻作りといろいろな仕事をやった苦労人ながら、そんな空気を微塵も感じさせないのが彼の魅力だ。
ヴィム・ヴェンダースの映画「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」で語っていたこのセリフは、90歳とは思えない艶やかな名言である。
ミュージシャンとしても男としても最期まで現役を貫いたコンパィは、2003年、95歳で静かに息をひきとった。
さ行
「できるだけ手を加えず、操作したり組み立てたりせずに、ありのままの音をそっと並べて、じっくりと眺めてみる」
坂本龍一(現代音楽)
あらゆる場所、時間、人物とコミットし、音楽という触媒によって、いくつものまったくちがった化学反応を起こしてみせる坂本龍一。
細野暗臣・高橋幸宏に誘われ「YMO」を結成したかと思うと、忌野清志郎(い・け・な・いルージュマジック〉を大ヒットにみちびき、ビートたけし・デヴィッド・ボウイとともに大島渚の「戦場のメリークリスマス」に出演、音楽を手がける。
同作が出品されたカンヌ映画祭で、ベルナルド・ベルトルッチに声をかけられ、『ラストエンペラー』に出演、本来やる予定のなかった音楽を急遽手がけたところ、アカデミー質作曲賞を受賞、「世界のサカモト」に。
バルセロナ・オリンピック開会式で指揮棒をふり、古本隆明、村上龍らと共著を残し、ダウンタウンをプロデュースする。縦横無尽である。
そんな彼がいつも帰る場所がある。ニューヨークだ。
9.11同時多発テロ、金融危機、世界をゆるがす震源地にあって、エゴにも敏感になる坂木。現在の音楽的境地を謡った言葉がこれである。
21世紀の音楽の、あるいは人間のあるべき姿を示しているかのようだ。
「放っておいて進んでいくものは何もないからな。自分で実現させなきゃならないんだ」
ジェームズ・ブラウン(ソウル)
ジェームズ・ブラウンは、樅貧家庭の棚立て小屋に生まれた。4歳で両親が離婚してからは、親戚の売春宿で育ち、万引きをして教護院へ放り込まれた。
出所後は、用務員などの仕事に就く。しかし、幼少期から得意だったダンスや圧倒的な歌唱力をいかし、1956年、〈プリース・フリース・プリーズ〉でデビュー。
絶頂期の帥年代は、1年のうち350冊ステージに立った。その間、作曲にもいそしみ、「俺が書いたのは、5500曲だぜ」(真偽不明)と豪語する。
80年代後期には、妻への暴行、無許可の拳銃所持、大統領の麻薬撲滅審議会のメンバーにもかかわらず、違法の鎮静剤所持などで、たびたび逮捕され、服役。
ところがこれがイメージダウンとはならず、伝説となってしまうのがJBだ。獄中唯活を満喫するため、4万ドルの大金を持ち込むことも忘れなかった。そして出獄後、何事もなかったかのように、ワールドッアーに繰り出した。
そんなJBが語ったのがこれ。ファンクの帝王という確固たる地位は、天賦の才能によるものではなく、巨大なエゴによって自らたぐりよせたものだった。
「ぼくが生み出す作品は、音楽への能力と、ぼくの苦しみとから生まれてくる」
シューベルト(クラシック)
美しい旋律の600以上の歌曲を書いたことで音楽史に多大な功絨を残したシューベルトだが、生前は日の目をあびることなく、貸乏暮らしに苛まれ、友人の援助でかろうじて作曲をつづける、しがない音楽家だった。
小柄でぽっちゃり型で、引っ込み思案、女性への接し方は不器用…。決して幸福には見えない人生に、追い打ちをかけるように襲ってきたのが梅毒。一説によると、26歳のころ、音楽教師としてついた伯爵家の召使いからうつされたようである。
不治の病にかかり、恐怖におびえるシューベルトが残したのが、このメモだ。
結婚はあきらめた。生きる糧は音楽だけ…。
「苦しみは理性を研ぎすまし、心を強くする」
絶望の深淵で、この世のものとは思えぬ音色を見出すシューベルトの過酷な闘争は、31歳のときに幕を閉じた。
「このドイツ人の想像にはほんとうに死ぬほど笑った」
ショパン(クラシック)
作曲したものは、ほとんどがピアノ独奏曲。ショパンは、ピアノを使って人の内面を描写した「ピアノの詩人」だった。
1831年、祖国ポーランドがロシアに征服された年、20歳そこそこのショパンは、激しい感情に蝋られながらパリ入りを果たす。
最初の数ヶ月は、演奏会の成功にもかかわらず経済的には困窮を極めた。
そんななか、ひとりのドイツ人がショパンを絶賛した。
「脱附しろ、紳士諸君よ。天才だ!」
この人物こそ、ショパンと同い年で、排諭活動も行っていたロベルト・シューマンである。
シューマンは、ショパンの曲の一小節一小節を分析し、好意的な評論を書き上げた。
ところが、その評論を読んだショパンは、冒頭のように言い、真に受けなかった。
それからまもなく社交界の寵児となったショパンは、次のようにも言っている。
「前より大ばかものになっていたとしたら自分は成功の絶頂にあると想像したかも知れない」
いつもクールなヴィルトゥオーソ(名演奏家)らしい言葉だ。
「ヒット・レコードなどなくても生きられることがわかりましたし、かえってないほうが幸せなのです」
ジョン・レノン(ロック)
1962年のデビュー以来、契約にしばられる形で、ひたすらヒット・レコードを作りつづけてきたジョン・レノン。ビートルズ初期には、1年に2枚のアルバム、3ヶ月ごとに1枚のシングルというノルマを課されていた。
プレッシャーから解放されたのは76年。周囲の反対の声を押し切り、息子ショーンの育児に専念することを宣言、主夫生活に入ったときだ。
はじめて訪れた家族との穏やかな時間。両親と生活した経験もないジョンは、生きることの喜びをかみしめた。
それから5年後、スタジオに戻ったジョンが語った言葉がこれ。
もしかつてのような過酩な仕事になるなら、レコーディングを打ち切るつもりでいたが、幸い、妻オノ・ヨーコとの共作という形で《ダブル・ファンタジー》は完成する。
リリース直後に射殺されたため遺作となったこのアルバム、ジョンが唯一にして真に音楽作りを楽しんだ名盤となっている。
「この世界で一番不幸な人とは、自分の仕事に満足していない人だ」
ジョン・レノン(ロック)
子供のころ、自分のあるがままを表現しようとすると、大人たちはひどい抑圧をかけてきた。
「たいていの場合、教師たちは私を歯医者だとか教師だとかになるようにむりやりしむけていた。
この葛藤を解決してくれたのが、エルヴィス・プレスリーだった。
「〃ハートブレイク・ホテル〃を聴いたときには、〃これだ!″と直感しました」
ロックン・ロールへの目覚め。このとき、ジョン・レノンは、音楽で自分を表現する道を見出し、それを生業とした。そんな彼の言葉がこれ。
それなりの特別な才能がなければ、好きなことを仕事にすることなど難しいと思われがちだが、そうではない。
「基本的な才能というものは、自分になにかできると信じることなのです」
あとは、実行に移すだけ。ジョンはそう言っている。
「もっとも重要なことは前のより良くなるってことだ」
シド・パレット(ロック)ヴォーカル
幻覚のような音色を生み出したピンク・フロイド。1967年のデビュー・シングル〈アーノルド・レイン〉は一般道徳を否定するような異質なもので、ドラッグを奨励しているとの理由でラジオで放送禁止になった。だが、ヒット・チャートはトップ20に登りつめ、バンドの人気は急上昇した。
ところがそのころ、ソングライティングを担当していたシド・バレットは現世に対する極度の恐怖症に襲われ、やがてケンブリッジの両親の家に引きこもってしまう。数々の奇行の果てにバンドとの調和ができなくなったシドは、翌年4月に脱退。
70年に2枚のソロ・アルバムを制作し、伝説の男の復活として音楽シーンを騒がせたが、72年春、スターズとして数回のギグを行ったのを最後に完全に姿を消す。
死亡説や入院説がささやかれ、生活扶助を受けながら絵を描いている、などといった伝説だけが肥大化していった。そして2006年、糖尿病に起因する合併症のため、60歳で生涯を閉じたことが報じられる。
ライヴで同じ曲を何度もプレイすることを嫌い、レコーディングではテイクごとに必ず新しい音を生み出していたシド。2枚のソロ・アルバム発表後、次回作について語っていたこのシンプルな言葉には「狂気の天才」のエッセンスがつまっている。
希望を告げる言葉
「この世は、その玄関先に拡がっている」
ジミ・ヘンドリックス(ロック)
1970年、ロンドンで謎の死を遂げるまで、世界で最も創造的なギタリストとして君臨したジミ・ヘンドリックス。
背中や頭のうしろで演奏したかと思えば、歯でギターをかき鳴らし、ライターのオイルをかけたギターに火をともす。
ワイルドで挑発的、セクシーなパフォーマンスは、ステージを降りても続き、群がる女性たちをベッドに誘った。
「ロードに出て困るのは、各都市を女で覚えていることだよ」とは、ジミヘンの言。
そんなスーパースターぶりを発揮した彼だが、実は、素晴らしく礼儀正しく、ほかのミュージシャンへの敬意も忘れない、高度な人格の持ち主だった。
1969年、それまで率いたエクスペリエンスを解散し、バンド・オブ・ジプシーッを結成、そのときの言葉がこれである。
互いに発展をつづけるためには、メンバー・チェンジは必然的に起こるもの、彼は冷静にそう考えていた。
いい音を出すためなら、変化を恐れず、日のあたる未来だけを見ていた。
た行
「必要とされるものは、デリケートな耳、すぐれた記憶力、前時代の断片を調和のある全体へと溶け合わせる力量である」
ドヴォルザーク〈クラシック)
19世紀、祖国チェコに伝わるスラヴ音楽から新しい音楽を生み出した、民族主義の作曲家ドヴォルザーク・当時、チェコはオーストリア・ハンガリーに支配されていたが、ドヴォルザークは生涯、愛する祖国で活動した。
だが、ニューョーク・ナショナル音楽院の学長に就任するため、3年間だけニューヨークに滞在したことがある。そのときに発表した、「アメリカにおける音楽」と題するテキストに収められた言葉がこれだ。
「前時代の断片を調和のある全体へと溶け合わせる」という言葉に、ドヴォルザークの音楽精神が凝縮されている。自分がスラヴ音楽から音楽を生み出すように、アメリカの作曲家たちも、アメリカ土着のインディアンや黒人たちのメロディから音楽を生み出すことが重要だと訴えている。
この考え方はアメリカで衝撃をもって受け止められたが、ドヴォルザークは自らその手本を示した。代表作、交響曲第九番〈新世界より〉である。〈新世界より〉は、スラヴ的な音にアメリカ・ネイティブ音楽の精神を溶け合わせて生み出された曲だった。
「芸術は、すべてのつくりごとのなかではもっとも美しいつくりごとです」
ドビュッシー(クラシック)
フランスの作曲家ドビュッシーの音楽は、「印象主義」と称されることがあるが、これはもともと否定的な意味で用いられたものである。
1884年、ローマに留学したドビュッシーは、芸術アカデミーのコンクールに交響組曲《春》を提出したが、「漢然とした印象主義」と批判される。従来の利声法にたよらない御きや辿りにくい旋律線が、アカデミーの反感を買ったのである。
これでアカデミーと決別したドビュッシーは、生涯、直観と感覚を重視し、言葉では表現しえない「心象」を呼び起こすことをめざした。
そんなドビュッシーらしい言葉がこれ。1902年に創刊された定期刊行物「ムジカ」のインタビューでの言葉だ。
彼は、つくりごとは日常のなかに組み込むことなく、「つくりごととしてそのまま残すようにしたいもの」と述べる。芸術のなかにまで日常を持ち込まず、芸術は芸術として堪能することが人事だということである。
は行
「人生には、お説教をうけるまえに、「食」と「愛」がまず必要だ」
ビリー・ホリデイ(ジャズ)
15歳の少年と13歳の少女とのあいだに黒人として生まれたビリー・ホリデイ。両親からは見すてられ、親族のあいだを転々とし、愛情に飢えた少女時代を送った。
不登校児となったビリーは、10歳で強姦にあう。人種偏見から被害者とはされず、不良少女の焔印をおされて感化院へ。14歳でニューヨークのハーレムの娼婦となる。
金にこまったビリーがむかった先が、ナイト・クラブだった。
泣いて仕事を頼むビリー、ピアニストの口添えでステージに立った。情感豊かな美声がホールをふるわせる。15歳の天才少女歌手、誕生の瞬間だった。
ビリーは、その歌声だけで一気に栄光への歩みをはじめ、ジャズ史上最高の名歌手となる。
しかし、生涯孤独にさいなまれ、麻薬と人種偏見に悩まされている。
聴く者を無条件に感動させる声、それは人生のあらゆる苦悩を味わったビリーの深い感怖表現がなせるわざ。そんな彼女が人生をつきつめ、はいた言葉がこれ。
宿命的に、「食」と「愛」が欠如していた彼女だからこそ胸に響く言葉である。
「最初に人であれ」
フー・ツォン(クラシック)
1955年、第5回ショパン国際ピアノ・コンクール、第3位に入賞したのは中国人のフー・ツォンだった。アジア人初の上位人賞という快挙。
それ以上に衝撃的だったのは、社会主義国として歩みはじめたばかりの混沌とした中国にあって、ほとんど独学でピアノを学んだ21歳の若者が、洗練された身のこなしで、ショパンのマッルカを創造力豊かに奏でたことだった。
中国では英雄扱い。だが、彼の人生は一転する。
4年後、中国国内の政治闘争を逃れてイギリス亡命を余儀なくされ、残されたフランス文学者の父フー・レイと母は、1966年、文化大革命の最中、危険分子のレッテルを貼られて首吊自殺フー・ツォンの胸のなかにいまも生きつづけている言葉がある。ショパン・コンクールへの旅立ちの際、父が授けたこの言葉である。
「どんなに教養があって立派な人でも、心に傷がない人には魅力がない。他人の痛みというものがわからないから」
フジ子・ヘミング(クラシック)
日本人ピアニストとスウェーデン人デザイナーを親にもつフジ子・ヘミングは、東京蕊大卒業後、ドイツ留学をめざすも国籍の問題でかなわず、29歳のときに避難民という形で渡独。
するとすぐに、バーンスタインらの推薦によってウィーンでのリサイタルのチャンスを得たが、直後に風邪で聴力を失ってしまう。
一瞬にしてピアニストとしての前途は絶たれ、彼女の前には音楽教師としての長く暗い日々が横たわった。が、1999年、NHKのドキュメンタリー番組でその様子が報じられると、一夜にして時の人となる。
有名になってもなお、他人の痛みに寄り添うことができるのは、あの絶望の日々があったから。米国同時多発テロ事件の被災者やアフガニスタン避難民のためなど、たびたび寄付を行うフジ子・ヘミング。そんな彼女の言葉がこれだ。
国内外で活躍するいまも、左耳が4割程度聴こえるだけで、右耳からはなにも聴こえてこない。そのピアノテクニックに疑問を投げかける論者は少なくないものの、神々しいやさしさ、深い人間性あふれる世界は、彼女だけのものである。
「なんて駄作だ!」
ブラームス(クラシック)
ハンブルクの貧困家庭に生まれたブラームス。家計を助けるため、喝歳のころから深夜の酒場でピアノ弾きのアルバイトをし、音楽家となってからは、作曲がたびたび酷評にさらされ、私生活では愛が成就することなく、生涯独身のままだった。
必然的に、性格は気難しくなり、音楽面では、自分の才能に確信がもてず、自虐的になった。
曲の構想はなんども練り直し、できた曲は、なんども書き直す。そして必ずこの言葉、「なんて駄作だ!」と書きなぐってから、友人に意見を求める。その意見をもとにまた書き直す。
少なくとも一回は演奏し、それで納得がいけば、ようやく出版社に送る。もちろんそこには「出版する価値なし!」と書きなぐることを忘れなかった。
こんな調子だから、大半の曲は途中で気に人らなくなって破り僻てられ、燃やされた。でもそれほど厳しい凹凸批判の態度があったからこそ、ブラームスの作品には珠玉の名曲しか残されていないのだ。
「運命の喉首をつかんでやる」
ベートーヴェン(クラシック)
音楽家としては致命傷となる、難聴の病に襲われたベートーヴェン。
彼が1802年に残した謎の文耆「ハイリゲンシュタットの遺苦」には、死か芸術かで苦悶する若き音楽家の姿がある。自殺を思いとどまらせたもの、それは「ひとえにぼくの芸術だった」とつづった彼は、同時期、交響曲第2番を完成させる。この曲には、遺言にも見られる内面の葛藤がまざまざと反映されている。
さらに、「運命の喉首をつかんでやる」というこの名言とともに、1803年からスケッチをはじめた交響曲第5番《運命》になると、感怖の起伏がよりはっきりした形となってあらわれた。図らずも、人生と音楽をリンクさせる手法は、ベートーヴェン音楽の真骨頂となった。これは音楽史的に言えば、客観性を帯びた古典主義から、主観を重視するロマン主義への大転換を意味した。
「世界は、ぼくたちがいなくてもまわりつづける」
ボブ・ディラン(ロック)
1965年、ボブ・ディランは、ギター1本の弾き語りスタイルから、エレキ・ギターやドラムを取り入れたロック・バンドスタイルへと変貌を遂げようとしていた
その年のイギリス・ツアーで、『タイム』誌の記者にあびせた言葉がこれ。
「…だから、あんたはそのことを踏まえて、どれだけ真剣にやるのかを決めてから、自分の仕事をしたほうがいい」とつづけた。
ディランは、めずらしくイライラしていた。63年にニューズウィーク誌が生い立ちを暴露してから記者への敵意を募らせており、リハーサルがうまくいかなかったことも重なって出たセリフのようだ。映画「ドント・ルック・バック」のカメラがまわっていたことから、演出ともいわれている。
とはいえ、つねに覚悟をもってのぞむ彼の生き様がにじみ出た言葉である。
同年、〈ライク・ア・ローリング・ストーン〉が録音される。これは、偽者全般に対する憎悪感を嘔吐のようにはいた怒りの歌。が、なぜか、人びとに理想や平和を連想させる名曲となっているのは、ディランの深い人間性によるものだろうか。
「いったん金にだめにされたら、友達は得られない」
ボブ・マーリー(レゲェ)
イギリス人の軍人とジャマイカ人の混血のボブ・マーリーは、レゲエ草創期の60年代半ば、学校の仲間とウェイラーズを結成した。72年、大都会の非情さを訴えたコンクリート・ジャングルを収めたアルバム《キャッチ・ア・ファイア》で、レゲエを国際的な音楽に押し上げた。
81年に36歳の若さで亡くなったが、いまなお〃レゲエの神様″として崇拝されている。
多くのアフリカ移民の黒人が貧困・差別にあえぐジャマイカにあって、ボブはいつも、弱者の側にあった。差別される側、何ももたない側に立ち、音楽を唯一の武器に闘った。そんなボブの言葉がこれだ。
もちろん本人は音楽的成功で高収入を得ていたが、金に踊らされることはない。金を介した人間関係しか築けない人にはこう言った。
「金を使い果たしたとき、あんたはおしまいだ」
日本風に言えば「金の切れ目が縁の切れ目」。万人への戒めの言葉である。
ま行
「それに僕は人間を芸術作品だと思っています」
マーク・ボラン(ロック「T・REX」ヴォーカル)
70年代初頭、グラム・ロックという甘美で刹那的なムーヴメントを牽引したT・REXのマーク・ボラン。「僕は30歳まで生きられない」という言葉通り、30歳の誕生日を2週間後にひかえた1977年9月、愛人グロリアの運転する車が街路樹に激突し、他界。グラム・ロックの永遠のイコンとなった。
この言葉は、ボランがアイドル視される以前の1969年、ティラノサウルス・レックス時代に述べたもの。レコーディング・セッションそのものが芸術であるばかりか、着こなし、しぐさ、話し方など、人びとのすべての個性が芸術だと語っている。
どこか懐かしさを感じさせる甘いマスクのジェントルマンで、外出を好まず、自宅で静かに詩作に耽っていたボラン。彼の豊かな人間性にふれる一言である。
「交響曲を書くことは私にとって、世界を組み立てることなのだ」
マーラー(クラシック)
19世紀末、ウィーンで活躍したロマン派の作曲家マーラーは、指揮者としても忙しい毎日を送っていた。
本格的な作曲の仕事はもっぱら夏のバカンスに集中。避暑地の作曲小屋にこもり、外界と隔絶。恐るべき産みの苦しみとともに、新たな世界を構築する。
そんなマーラーの言葉がこれ。
生来の楽天主義と、兄弟姉妹7人の死や両親の絶え間ない喧嘩を味わった苦い体験。マーラーの情緒豊かな音楽世界は、この二面性を反映している。
「まるでそれはまったく自分で作ったものではないような想いがする」と本人が述べるほど、すべては深い沈潜をへて生まれている。
「自分がみんなよりすぐれているなんて考えたりしない
みんな同じ人間なんだ」
マイケル・ジャクソン(ポップス)
少年への性的虐待疑惑、偽装結婚、多大な借金問題など、スキャンダルの宝庫と化した90年代以降のマイケル・ジャクソンは、一般には嘲笑の対象となっていた。
その姿は、人びとから疎んじられ、金策に苦しんだ晩年のモーツァルトと異なる。もしかしたら、音楽的価値においてもモーツァルトに匹敵し、数百年後、研究の対象となる可能性さえある。ロックとファンク、ホワイトとブラックを融合したマイケルの功績は無視できない。
この言葉は、ザ・ジャクソンッとソロ活動を両立させ多忙を極めていた4歳のマイケルのものだ。そこには、圧倒的な歌唱力と複雑なダンス・ステップのテクニックをもちながら、白分の才能を過信することのない純朴で控え目な青年の姿がある。
「思い上がるな!」と両親から口酸っぱく諭され、慢心を排してストィックに向上しようとする青年マイケル。
数年後、容姿修正をへて《スリラー》でセンセーションを巻き起こす。
「自分自身を知ってそれを愛せるようになった時、本当に愛される人間になれるんだわ」
マドンナ(ホップス)
目がくらむような美女でもなければ、とくべつ歌がうまいわけでもない。
そんなマドンナが、〈ライク・ア・ヴァージン〉で世界を席巻し、ポップ・ミュージック界に影響をおよぼすビッグスターになったのは、デビュー当初から「世界を制してやる」と公言する野心家だったこと、そして鍛え上げた肉体とストィックな精神で、ハードな仕事を完壁にこなす努力家だったことによる。
ハングリー精神むきだしのときの歌は、わがまま、自己中心的、挑発的ととられることもあったが、自らの言動がばらまくスキャンダルがPRになることは、ハイスクールでIQ140の優等生だった彼女にしてみれば、計算のうちだったはず。
しごと一本だった彼女の人生が変わったのは、1996年、最初の子供ルルドを授かったとき。
母となったマドンナは、本来の女性としての魅力を磨き、本当に愛される人間となっている。
「素晴らしい音楽を創造するためには、クソみたいなレコードを山ほど聴かなきゃならないんだよ」
ミック・ジャガー(ロックヴォーカル)
ぼさぼさの髪、卑猴な歌詞…。ローリング・ストーンズのグループイメージは、ビートルズを意識してデビュー時につくられている。ビートルズがよく磨き抜かれた紳士ならば、ローリング・ストーンズは粗野な不良というわけだ。
楽曲だって、ビートルッを意識した《サージェント・ベバー》に対して〈サタニック・マジェスティーズ》、《レット・イット・ビー》に対して《レット・イット・ブリード》。
この言葉は、60年代後期、ほかのアーティストの影響を受けているかどうかとの問いに、ミック・ジャガーが答えたもの。……完全に開き直っている。
ミックには、パクリじゃないかという非靴も甘んじて受け、それを強力に跳ね返すだけの爆発があった。
才気溢れる言葉
「わたしには、完ぺきではない音楽のつくり方がわからないんですよ」
モーツァルト〈クラシック)
5歳で作曲をはじめ、14歳のときにはオペラを書き、大人の作曲家でも難しい対位法の問題をやすやすと解いた、神童モーツァルト。
オペラ、交響曲、協奏曲、室内楽、宗教曲、ピアノ・ソナタ…。彼に不得意なジャンルはない。生涯に書いた600以上の曲すべてが傑作。人の話を聞きながらでも曲をつくり、自筆譜は一ヶ所も書き直しがなく清書したようにきれいだった。
自筆譜が書き直しで汚れ、オペラは1作しかないベートーヴェンと比べてみると、その天才性はより際立つ。
「いつもこんなに完ぺきな音楽を、いったいどうやってつくっているのか」
と、尋ねた人へのモーツァルトの答えがこれ。
彼をおいてほかにこのセリフを言える音楽家はいないだろう。
「望みを持ちましょう。でも、望みは多すぎてはいけません。多くのことをなす近道は、
一度にひとつのことだけすること」
モーツァルト(クラシック)
少年時代は神童ともてはやされたモーツァルトだったが、青年時代は就職雌に悩まされた。「職探し」の音楽旅行では希望の宮廷音楽家の職が見つからず、地元ザルツブルクの大司教のもとで奴隷のように働かされた。
帷機が訪れたのは25歳のとき。大司教との大喧嘩の未、父の反対も押し切り、ウィーンでフリーランスの音楽家として独り立ちする。解放されたモーツァルトは、演奏会や作曲活動などを通してその才能をおしみなく披露し、最高の音楽家として認められる。だが、浪費癖もあって、死ぬまで経済苦に悩まされた。
「望みは多すぎてはいけません」というこの言葉からは、決してその才能に見合った地位に就けなかったモーツァルトの慎重な姿勢が見てとれる。
人気音楽家として多忙を極めたウィーンでの生活は、朝6時起床、床屋が来て身なりを整え、7時から9時まで作曲、9時から午後1時まで生活費を稼ぐためのレッスン、それから夜にかけては、食事会や淡奏会などがあって、就寝は深夜1時。
1日わずか2時間程度しか作曲の時間がなかったにもかかわらず、多作で、しかも駄作がなかった。どんなに忙しくても、「一度にひとつのことだけする」という術を会得していた結果だろう。
や行
「作るのではない」
山田耕作(クラシック)
《赤とんぼ》《この道》などの童話で知られる山田耕作。西洋で最初に認められた日本の作品であり、日本の西洋音楽の発展に尽くした人物である。音楽の教科書でもおなじみの顔だ。耕作がドイツ留学から帰国後、1935年発行の「耕作楽話』に書いた言葉がこれだ。
「作るのか生むのか」のテーマで、「作るのではない」と耕作は答える。これにつづき、「生活から生むといふのが私の刺作上の信条だ」としている。
創作そのものは、「音が心耳に聞こえて来る」ので、それを書き閉めるだけでたやすい。だが、その前提には、「いささかも油断のない、全く言語に絶えた、真剣な生活そのもの」がある、と耕作は告白している。
「誰も歩いたことのない道を切り開きたい」
吉田拓郎(フォーク)
このセリフのとおり、吉田拓郎は日本の音楽シーンの新しい道を切り開いた。
それまで社会や政治との関わりが深く、汗と泥のイメージがあったフォークと決別し、明るさのあるフォークをはじめて歌ったのは拓郎だった。
その象徴が、72年の〈結婚しようよ〉。この一曲で拓郎は、既存のフォーク・ファンを敵に回したが、新たなファンをごっそり獲得した。
75年、「つま恋」野外オールナイト・ライヴでは7万5000人を集めた。それまで1万人がせいぜいだった日本の音楽イベントでこれほどの人を集めたのは空前のことで、ひとつの伝説をつくった。
さらに同年、小室等らとレコード会社を設立。社長業にも挑戦。アーティストがレコード会社をもつというのは、当時としては革命的な出来事だった。
アイドルでも俳優でも演歌歌手でもないのにスターになった拓郎。彼は、70年代以降の日本のアーティストの新たなスタイルを築いたのである。
ら行
「ソウルがどんなものだかはよく解らないが、それは部屋を明るく照らし出すある力なのだ」
レイ・チャールズ(ソウル)
サザンオールスターズのカバー曲《いとしのエリー》で、日本でもその名が知れ渡った、〃ソウルの神様″こと、レイ・チャールズ。
素晴らしい技巧のピアノ、耳に心地よいだみ声。ゴスペル、カントリー&ウェスタン、ラテン、ジャッ、ブルース、ポップス、ロック、どんなジャンルの曲であろうと、彼独特のフィーリングにかかると、心に染み入る音楽世界となる。
生涯、父親と顔を合わせることはなかった。6歳のとき最愛の弟が目の前で溺死した。その2年後、緑内障が視力を奪い、光を失った。
「いつか母さんは死ぬ。その後、お前は一人でやっていかなきゃならないんだ」と、母には厳しく育てられた。その母は15歳のときに亡くなった。
天涯孤独となったレイにとって、生きる術は、(愚かにも人種分離された)盲学校で学んだ音楽。音楽は、幼少のときにたしかに記憶した網膜の映像…。太陽、月、母親の黒髪などを再生させ、この世の美しい場所へと誘う。
レイにとって音楽は、漆肥の間を明るく照らし出す、希望の光だった。
「あなたが音楽家になろうと思ったときから、あなたは音楽家なのだ」
レナード。バーンスタイン(クラシック)
20世紀後半の偉大な指揮者のひとりであり、ピアニスト、作曲家としても才能を示したバーンスタイン。ジャズやポピュラー音楽など、あらゆるジャンルに精通し、《ウエスト・サイド・ストーリー》の作曲によって、ブロードウェイのミュージカルを芸術の高みにまで引き上げたことはよく知られる。
ベトナム戦争や人種差別については反対の意思を表明。教養人で外向的、他人に対する丁重さを忘れない、唯一無二の人間性は、多くの人びとから愛された。
そんなバーンスタインの名言がこれ。子供のときに音楽の虜になってから、音楽の道をまっすぐに歩んできたバーンスタインらしい言葉である。
プロになれるかどうかなど考えることはナンセンス。音楽をやりたい欲求があるのにあきらめることは、自分が存在しないも同然、と彼は言う。
「そうしたいと思うときに遂行するために生きているのです」
わ行
「私は、私自身の主人でなくてはなりません」
ワーグナー(クラシック)
ドイツの音楽家ワーグナーは、いつも逃げていた。
ロシア領リガの劇場指揮者のときには、借金がかさみ、債権者たちの目を逃れてパリへ逃亡。パリでは、一時刑務所に入ったという逸話もあるが、これは友人から金をせびり出すための芝居だったようだ。ドレスデンでは、1849年の革命にかかわったため逮捕状が出て、スイスのチューリッヒに逃亡。10年以上、亡命生活を余儀なくされた。ドイツ帰国が許されてからも経済苦で各地を指揮してまわった。
救いの手がさしのべられたのは、50歳も超えた1865年のこと。ワーグナーの音楽を崇拝していたバイエルン国王ルートヴィヒ2世が援助を申し出て、全負債を清算し、ミュンヘン近郊のシユタルンベルク湖畔に邸宅まで用意してくれたのだ。
このとき、知人に宛てた手紙にある言葉がこれ。自尊心が強いワーグナーは、王に敬服しながら、都合のよいお抱え音楽家になるつもりはないことを表明している。
公金を浪費するワーグナーには、王の側近から非難が絶えなかったが、そんな圧力にも屈しなかった。彼は、怖い王を巧みに操り、創作環境を充実させ、自作の楽劇を上演するためのバイロイト祝祭劇場を造るなど、わがままな芸術活動を死ぬまでつづけたのである。
- アーティストを目指してできるインターネット利用方法やデモテープ作成方法
- どうしてもカラオケで高得点をとりたい人のためにできる方法
- 音楽用語辞典|解説付きで簡単に検索できる
- カラオケ店舗選びに最適!カラオケ店舗比較ランキング